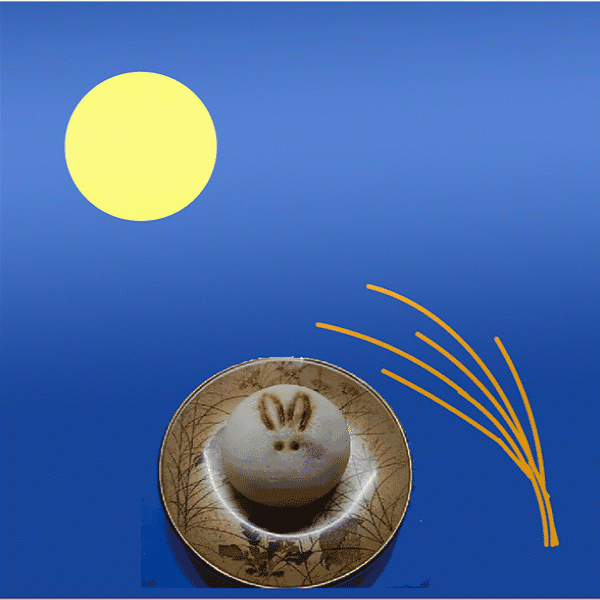広告
中秋の名月
秋の真ん中頃のことを中秋と呼びます。立秋から11月頃までの真ん中。陰暦8月15日が中秋の名月となります。
名月を祝う行事は各地で行われますが月を愛でるのは私たち日本人だけかもしれませんね。
9月13日(陽暦)は
♪う~さぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月さん見て跳ね~る♪ と歌われる
中秋の名月、 ススキや団子を供える風習が今でも残っています。
古来、日本人は生活の折目として月を愛でてきました。
米や農産物の収穫時期に、自然の恵みに感謝し拝むという風習があります。

月の呼び方にもいろいろあります。
中秋の名月
十六夜
有明の月
後の月
良月
弦月
無月など数え切れないほどあります。
秋風に たなびく雲の たえ間より 漏れ出づる月の 影のさやけさ
(百人一首 七十九番歌 左京大夫顕輔)
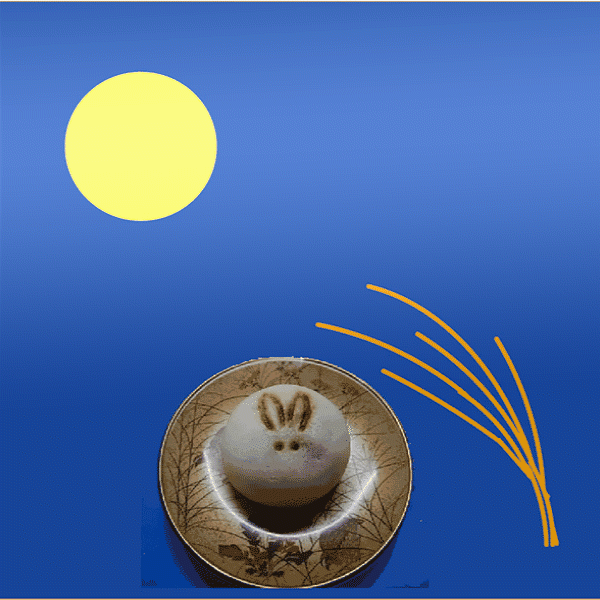
十六夜(いざよい)
いざようとはためらいながらという意味で、十五夜の後に出てくる月を十六夜と呼びます。名月の後にためらいながら出てくる月も日本人的ですね。
地球が生まれた時は月は存在しなかったということです。
潮の満ち引き、睡眠摂食など人間の生活にとって無くてはならない月、太陽の反射によってできる月あかり、そんな月を眺めながら物思いにふける秋です。
月見れば 千々に物こそ 悲しけれ 我が身ひとつの 秋にはあらねど(百人一首二十三番歌 大江千里)
月を見ると千々に物事が悲しく感じられてしまうなぁ。私一人の秋ではないのに。
秋はいつの世も物寂しくなるものですね。
広告